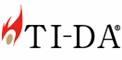基地移転問題について思うこと
びん教授のブログを見ていて思ったのですが、やっぱり沖縄の現実から目をそらしていてはいけないと思うので今回、書きます。ですので、だいぶ文体変わりますがお許しを。
今回の「辺野古移転」は96年の普天間返還合意(橋本・クリントン)を受けたSACOの報告から始まった話である。実際、普天間基地は宜野湾市のほぼ中央に位置しており、しかも那覇のベッドタウンというようなところにこれだけの基地があるというのは本土ではまずありえない話であろう。しかも、である。市のど真ん中に普天間は存在し、日々騒音を撒き散らしているのである。このことについては「写真集 沖縄」(1970 沖縄革新共闘会議編 新時代社 絶版)の写真を見れば一目瞭然である。あまりの騒音のため、周辺の学校の窓は2重構造になっており、防音工事もされている。しかし、そんなものは騒音の前では無力であり、現在でも近くの小中学校や高校、大学などは飛行機の離着陸時になると一旦教師がしゃべるのをやめてしまうそうである。うるさすぎて授業にならないからだそうだ。で、静かになったら授業再開となるらしい。
この写真集は当時の沖縄の現状を知るうえで重要な資料となると思う。実際に70年代当時でまだコンセットの学校が存在していたのである。このコンセット校舎が鉄筋になったのはやはり屋良朝苗琉球政府主席の力が大きいと思う。
また、基地の現状(というか70年代当時に存在した施設)の説明も多くある。実際にこの中の写真で国頭村の写真があるが、「BOAの強力な電波で電球がソケットにつながなくてもつく」という写真である。こんな強力電波が人体にいいはずが無いと思う。現在は返還されたハンビー基地もこれにはちゃんと記載がある。あと、核弾頭施設の「メースB」は現在某宗教団体の所有となっている。
話が脱線してしまった。元に戻そう。
今回の移転については正直「?」である。しかも、移転費用は全て日本持ちというわけのわからない事態が発生している。そもそも「日米安保条約」なるものの根拠がおかしい。アメリカ側は1854年の「琉米修好条約」を根底に据え、その上で1951年の「日米安保条約」を提示してきているのである。したがって、「日本はアメリカの補助さえしてくれればいいのだ」という考えがアメリカ側にはあると思う。確かに、戦後日本はアメリカからの資金援助によって成長したという一面もあるのだが、そろそろアメリカ側も「世界の保安官」などという傲慢な論理を取り下げたらどうかと思う。現在のアメリカは戦前の日本の状態とそっくりである。「京都議定書」をを無視しても自国の産業発展を選んだということは結局「俺がよければ全てよし」とする自分勝手主義の最たるものであると思う。普天間の海兵隊がグアムへ移転することにしても、その費用はアメリカが出すのではなく、日本が出すのである。こんなバカな話があるだろうか?在韓米軍が撤退するときには韓国側は金は出さなかった。「撤退するなら勝手にやってくれ」というスタンスだった。しかし、日本はといえばアメリカの属国と化しているので「へへ~っ、アメリカ様は世界一ですだ~」という強者におもねる論理が通用しているのである。確かに私は右寄りだと言われることもある。しかし、こうしたことについてはきちっと言う、こうしたバランス性というものが重要になってくるかと思われるのである.
4・11
びんさんより「沖国大ヘリ墜落ではなく「辺野古移転」」は、96年の普天間返還合意(橋本・クリントン)を受けたSACOの報告から」というご指摘をいただき
ました。これは私の調査不足でした・・・。訂正いたします。
関連記事